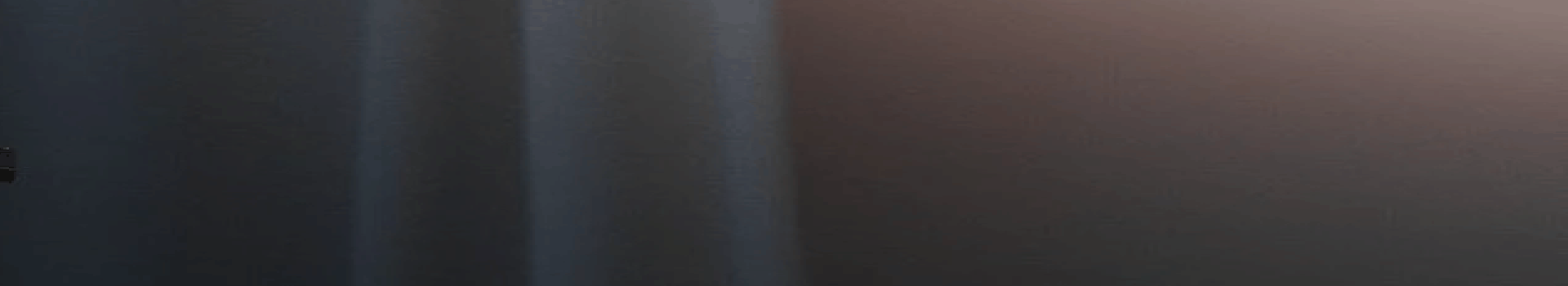LED ディスプレイのリフレッシュレートを理解する:包括的なガイド
リフレッシュレートの定義と重要性
LEDディスプレイのリフレッシュレートは,Hertz (Hz) で測定される画面が1秒間に画像を更新する回数を指します.60Hzのリフレッシュレートは,ディスプレイを1秒間に60回更新します.高速なリフレッシュレートは,よりスムーズな動きを保証し,点滅を軽減し,視聴者の快適さにとって重要な視覚安定性を向上させます.
2. フレームレート vs フレームレート
リフレッシュレートとフレームレート (FPS) は,しばしば混同されるが,異なる役割を果たす.リフレッシュレートは,LEDディスプレイがコンテンツを更新する頻度を決定するハードウェア属性である.フレームレートはビデオファイルの属性です., 画像情報が1秒間に更新される回数を表示し,単位はHz (ヘルツ) である.フレームレートとリフレッシュレートの不一致は,画面の裂け目とタタリングを引き起こします.視覚機能に重大な影響を与える.
3. 共同更新基準
3840Hzのリフレッシュレートは,幅広いアプリケーションに適しています.XRコンテンツ作成や高級放送スタジオなどの高級産業は,7680Hzディスプレイの優れた動作処理を必要とします..
4. 更新速度の技術的決定因子
リフレッシュレートは主にLEDドライバチップとスキャン方法によって制御されます.
ドライバチップ:LEDディスプレイのリフレッシュレートは,LEDドライバチップと密接に関連しています.ハイエンドドライバチップは3840Hzまたは超高い7680Hzのリフレッシュレートを達成することができます.
スキャン方法:LEDディスプレイのスキャニング方法は,その列駆動方法,特にピクセルの列と列を駆動する際に使用される"時間分割多重化" (TDM) 式を指します.通常は, scan1/N scanとして表されます (Nは行数を表します).
A. 静的スキャン (1/1スキャン): すべての列のピクセルが同時に点灯し,列ごとにスキャンする必要がなくされる.
B. 1/4 スキャン: 画面全体が4列のグループに分けられ,各グループの1列を同時に照らす.
TDMベースの運転スキームを使用することで,必要なドライバーICの数が減少し,特に大きなLED壁に有利です.
スキャン方法がリフレッシュ速度に与える影響
スキャニングドライブ方法 (非静的スキャニング) では,全体的なリフレッシュレートは行スキャニングサイクルによって制限される.全体のリフレッシュレートは F (Hz) で スキャンレートは 1/N (N は行数),各行が1/(FxN) 秒ごとにリフレッシュする.スキャン番号 N が増加した場合 (例えば 1/4 から 1/16 に),各行リフレッシュの利用時間は短くなる.このドライバーチップは,より速い行切換速度を持つ必要があります,そうでなければ,全体的なリフレッシュレートは改善できません.
A. 静的スキャン (1/1):行スキャン遅延がないため,3840 Hzを超えるリフレッシュレートを達成するのが最も簡単です.
B. 高スキャン速率 (例えば1/16): 列運転速度を高く要求する.ドライバーICの性能が不十分である場合,リフレッシュレートの上限が低下する可能性があります.
5視覚的快適性と撮影への影響
視覚的 快適性: 画面 を 長く 見る と,リフレッシュ 速さ が 低く なら,目 の 疲労,乾燥,その他の 不快感 が 引き起こさ れる こと が あり ます.リフレッシュ 速さ が 高く なら,人 の 目 に 感知 できる 点滅 が なくなる.長期間の視聴中に疲労を軽減し,観客の持続的な視覚的快適性を確保する.
撮影性能:映画およびビデオ制作では,高リフレッシュレートはカメラが"スキャン線"または"黒いフィールド" (LEDがオフになったときの短い間隔) を撮影するのを防ぎます.ブラックフィールドの期間を大幅に短縮することで記録された映像の画面の点滅や暗い領域を回避し,ショットの連続性を向上させ,シームレスな移行を保証します.
6産業の動向と勧告
3840Hzのリフレッシュレートは幅広いアプリケーションで好ましい選択になりつつあり,7680Hzは現在超高級用途に採用されています.例えばXR. リフレッシュレートを選択する際には,意図されたアプリケーションを考慮してください. ライブイベントや映画制作などのアプリケーションは,しばしば高いリフレッシュレートを必要とします.制御システム目標のリフレッシュレートをサポートします
リフレッシュレートは,LEDディスプレイのパフォーマンスにおいて重要な要因であり,視聴体験と没入的な仮想撮影に大きな影響を与えます.リフレッシュレートの仕組みを理解することで,消費者と専門家の両方で情報に基づいた意思決定が可能になります.

 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。 メールを確認してください!
メールを確認してください!  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。 メールを確認してください!
メールを確認してください!